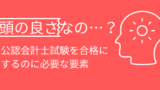みなさんこんにちは、公認会計士短答式試験→論文式試験に税理士法人で働きながら合格したsuiです。
この記事では、
✔具体的に財務会計論ってどんな風に勉強すればいいの…?
✔どれだけ勉強すればいいの?
✔点数が上がらなくて心が折れそう…
そんな疑問や悩みに答えていきます。

筆者は本番172点とりました(自慢気)
短答式試験における財務会計論の位置づけ
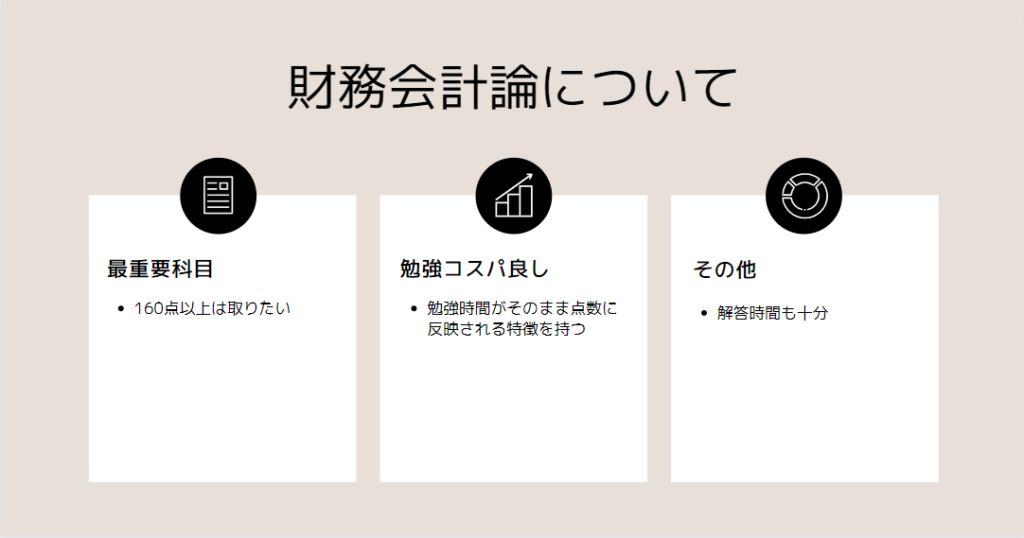
先ずは、社会人受験生にとっての短答式試験の位置づけにおいて確認していきます。
財務会計論は本番で160点以上たたき出さなければいけません。
理由としては、
✔配点が200点と大きい
→時間が足らない社会人受験生はここに勉強時間を集中させるほうがコスパがいい。
✔すべての問題を解ききることが可能な時間設定
→管理会計論と違い、すべての計算問題で7分程度は検討する時間がある。
その為実力が点数に反映されやすい。言い換えるなら、勉強が無駄にならない
「理解していれば答えが出せる問題が多く、十分に問題に取り組む時間も確保されている科目」といえます。
以上の理由から財務会計論は配点が多いうえに勉強した分だけ点数が伸びやすい、
夢のような科目です。

財務会計は本当に裏切りません…
どう勉強するのか
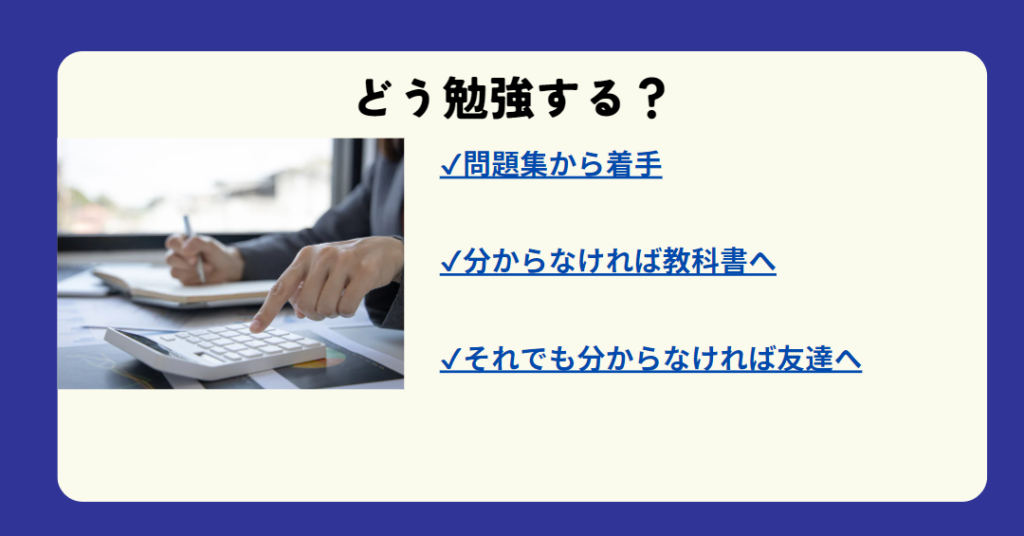
問題集→教科書→映像授業の順で勉強を進めてください。
より細かく説明すると、
問題集を解いてみる→1ミリも分からない→教科書を読みながら解く
→どうしても納得できなければ映像授業を見る
こんな感じの流れになります。
実際にやってみると実感できますが、映像授業を見て「なるほど…!!」となるタイミングは10回に1回もありません。
より正確に言うなら、財務会計論で7割を超えたあたりから映像授業を見ると価値を見出せるタイミングが増えます。授業で言っていることは95%は教材と同様の内容です。そして残りの5%は理解が深まっていないとその価値に気付けません。
正直5%を探すために映像授業を見るくらいなら友達に質問するほうが10倍効率が良いです。成績優秀な友達を作ってください。
以上の内容を振り返ると、こんな感じの行動パターンになると思います(実際の私の勉強サイクル)
問題集(答練)を解く→分からなければ教科書→さらに分からなければ友達に聞く
点数が上がらないあなたへ
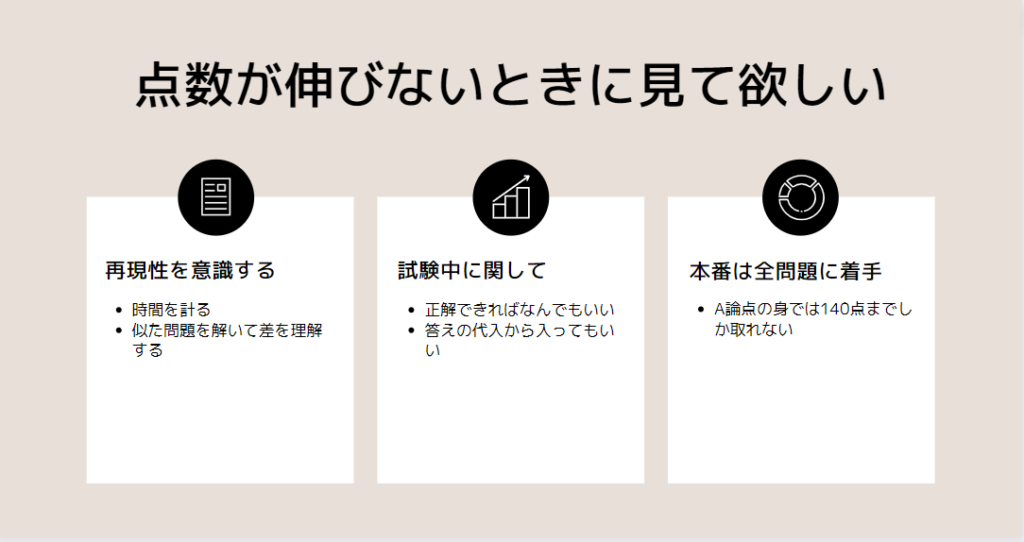
模試や答練で160点以上を出すのはすごい大変です。
点数が上がらない原因はシンプルに勉強時間不足のパターンが一番多いです。
社会人受験生でも、財務会計論だけは専念組と同程度の勉強時間を突っ込んでください。
(企業法や監査論を薄くしましょう)
点数の上げ方に関してはこちらの記事でも書いているので是非見てみて下さい。
勉強中に意識すること
✔再現性のある理解をする
→問題を解くときに、なるべく抽象的な理解まで物事を落とし込んでください。
例えばリースの問題だったら、「残価保障の場合は残存簿価と減価償却がポイント」
のように、試験本番の問題文でそのキーワードが出たら論点はどこになるか把握できるようにして下さい。
※慣れてくると、論点分だけ答えがズレた選択肢があったりするので、セルフで検算できたりします。
✔論点ごとに必要な所要時間を計る
→財務会計論といえども時間が余裕なわけではありません。社債やリースをひねって出題されると時間が溶けていきます。手間取っている問題は、頑張っても正解にたどり着ける可能性が低いです。
例えば、私の場合だと一般的なリースの問題なら正解まで6分でした。逆に7分以上時間がかかってるときは上手く解けていないと分かります。
✔「差」を理解する
→得意な論点の問題を間違えたとき、いつもの問題とどこが違うのかを比べてしっかり理解して下さい。リースならリースの問題の束、資産除去債務なら資産除去債務の束を作って、問題ごとの「差」を確認して下さい。論点は比べたときに浮き上がってきます。
間違えた問題だけを見ていても、自分がどの論点を理解できていないか明確にすることは難しいです。答練はバラバラにして論点ごとにまとめることをお勧めします。
※この勉強法をしていくと、リース・社債は特に問題のバリエーションが豊富なことに気付けると思います。意外と頻出論点は抑えるべき部分が多く、本番に正解し難いです。

ストックオプションはブチ切れて
ありとあらゆる答練を束ねました
試験中に意識すること
✔正解を選べていればなんでもいい
→正解できれば解き方なんてなんでもいいです。初見の問題は解き方として、代入or理論の知識から計算を行う。以上の2パターンです。140点~150点までは基礎的な知識と訓練で行けますが160点は初見の問題を半分は正解しないと到達できません。
1度でも答練や模試で140点を超えたことがある人は既に基礎知識が固まっています。残り20点を積み上げるためには順序だてて物事を解くというスタイルを捨てて、正解の選択肢を如何に選ぶかということにフォーカスして下さい。
✔全問題に着手する。
2021年5月の短答式試験の私の点数構成がこんな感じでした。
※難易度は大原参考。
A論点14/15(約90%)
B論点 7/9(約75%)
C論点 3/4(訳75%)
個別問題3問ミス、総合問題1問ミス.
合計172点
→想像していたよりもB論点、C論点もしっかり点数を稼げているように感じませんか?
確実に140点を取るために、基礎問題をすべてじっくり時間をかけて正解する戦略は間違いだと思います。この戦略は自ら満点を140点に狭め、かつノーミスで正解しなければなりません。どうあがいても本番で凡ミスを2問はすると思います。上記の戦略を取った人のほとんどが本番130点台程度でフィニッシュするのではないでしょうか。財務で140点以下を取ると社会人受験生は専念組に、企業法・管理会計論・監査論で負けます。
160点の取り方としては、A論点124点(8割~9割)、B論点24点(6割~7割)、C論点16点(5割)といった感じで、応用的な問題や初見の問題であろうと全部あてに行ってください。

丁寧に解いても雑に解いても、正答率はそんなに変わらないで
まとめ
✔財務会計論は160点越えを狙う
✔問題→教科書→友達
✔B論点、C論点を取りに行くメンタル
この記事を読んでくれた人に次に読んで欲しい記事
①財務会計論の次に力を入れるべき管理会計論について
②会計士試験に自分が向いていないかもしれない…と思った時に読んでほしい記事
③財務に強くなる予備校は大原だと思う記事