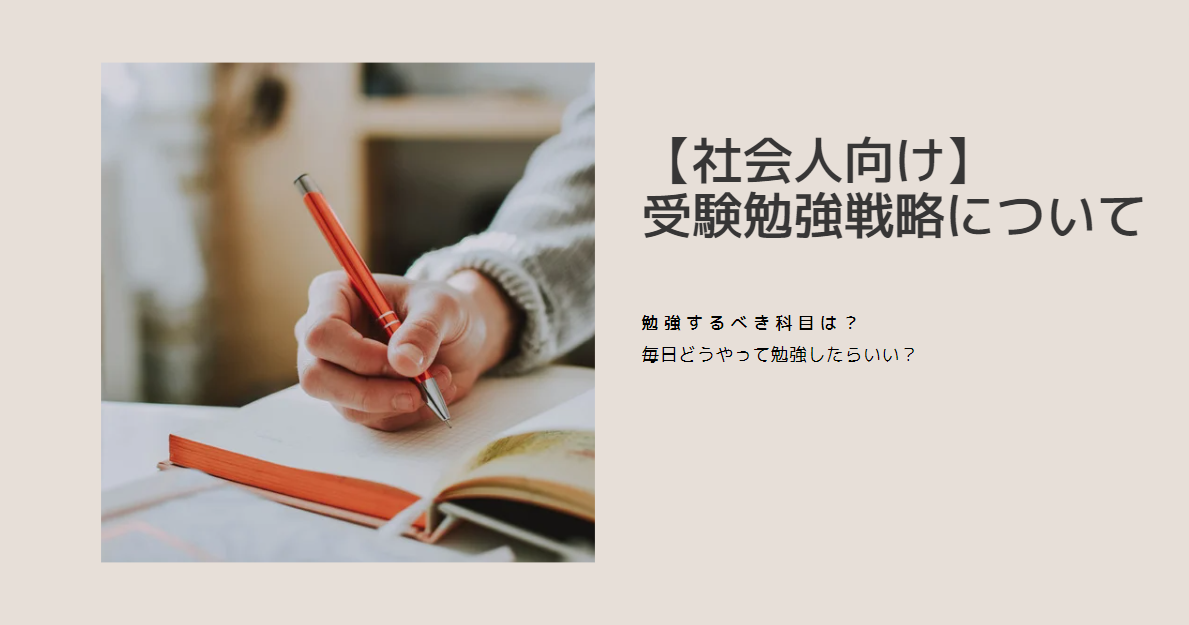みなさんこんにちは、公認会計士短答式試験→論文式試験に税理士法人で働きながら合格したsuiです。
さて、ほかの記事でも紹介しましたが、
社会人受験生はとにかく時間がありません。
この記事では、
✔社会人受験生のメリット
✔社会人受験生のデメリット
✔実際にどのように競争に勝っていくのか
✔社会人受験成功に欠かせない要素
以上の内容で記載します。
社会人受験生のメリット
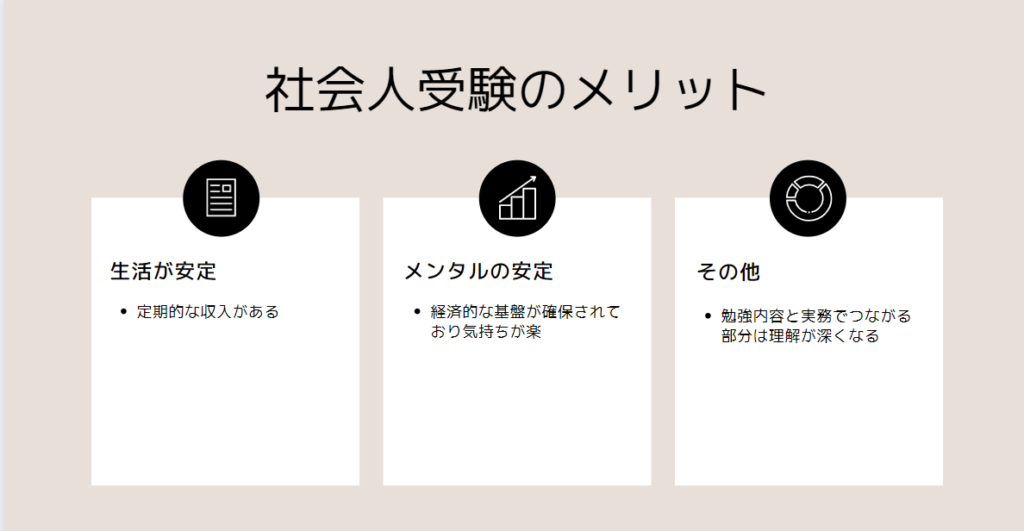
✔生活が安定している
✔万が一諦めた際でも仕事についているため、何とでもなる
社会人受験生には、勉強時間の確保が難しいこと以外にデメリットがありません
これは大きなメリットで、空き時間を勉強に心置きなく投入できます。受験時代の友人には、学生受験生や専念受験生がいましたが、彼らは例外なく周りが遊んでいたり、働いていることと自分を比較して悩んでいました。
また、専念組や学生受験生は常に「撤退」という文字が頭にちらつきながら、勉強・試験本番を迎えています。その点働きながらであれば、覚悟さえ決まれば仮に落ちたところで次の試験まで日々のルーティーンを繰り返しているだけでいい為、過度な緊張感を感じにくいと思います。
また就職先によっては仕事内容が勉強とリンクして点数があがることもあります。監査法人のトレーニーで就職出来たら、監査論に詳しくなるでしょうし、私のように税理士法人に勤めると、財務諸表論と租税法は勉強と実務が結びついてテストの点数があがります。

↓に働きながら合格するための就職先について検討してします
社会人受験生のデメリット
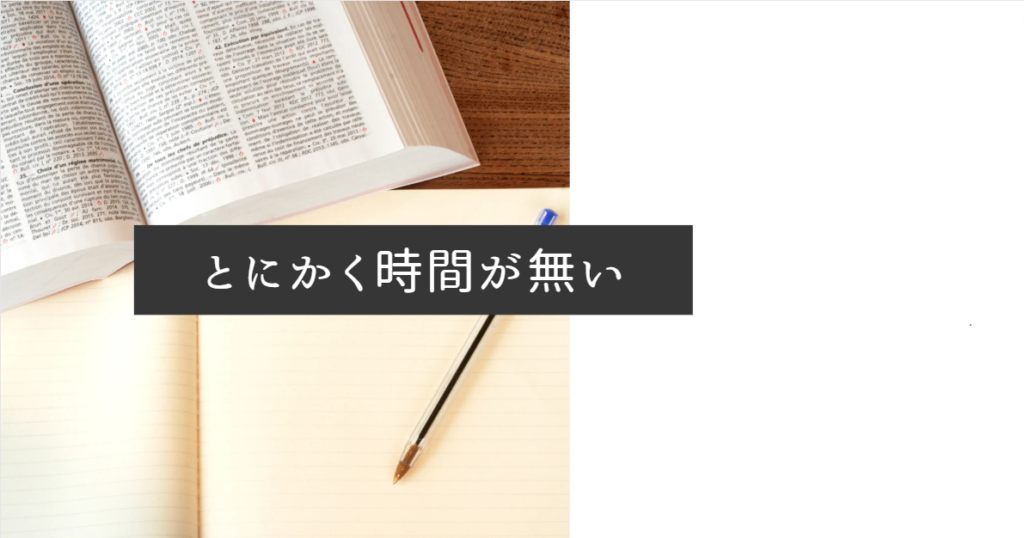
✔勉強時間の確保
✔プライベートの時間の確保(結婚している場合や恋人がいる方の場合)
皆さんが想像する通り、圧倒的に時間が足りません。
働きながらの受験をしていると、そのうち1日24時間のうち何に何時間を使うかを計算するようになります。友達、彼女、妻、娯楽に時間を費やすということは勉強の時間を捨てているという機会損失の認識が急速に高まり、一時的にすべての物事を投下時間とそのリターンで判断するという経営者もびっくりな思想に変貌します。
1日の時間配分のイメージ:
平日の場合、1日の勉強時間がMAX5時間しか取れません
平日4時間×5日+休日10時間×2日で
週40時間を死守できれば、日本有数の社会人受験生になれます。
24時間のうち、8時間は睡眠・8時間は仕事と考えると1日の勉強時間は理論上8時間しか確保できません。
現実的には、8時間の勉強可能時間を、
・歯磨き、シャワー、朝ごはん等の朝の準備
・通勤時間
・昼食
・夕食、お風呂、掃除、洗濯
・残業
上記のものが、最低でも2時間半~3時間奪っていきます。ここに交友関係のコミュニケーションの時間を入れてしまうと勉強のルーティーンが一気に崩壊します。
事実上、生きることとと勉強以外のことは出来なくなります。本気で働きながら合格を目指すなら身辺の整理と周りへの理解を本気で得ることが必要になってきます。

妻や彼女とギスギスすると勉強に集中できなくて、結局自分が損するから早めにコミュニケーションしよう
実際にどのように勉強していくか

✔受験自体の戦略(短答式)
受験戦略についてですが、先ずは短答式について書いていきます。短答式試験を通ることが最も困難だからです。逆に論文式にたどり着けば継続して勉強できれば合格は見えてきます。
結論、財務会計論で160点~170点を取ってください。
他の科目は60点取れればそれでいいです。イメージとしては、
企業法60点
管理会計論60点
監査論60点
財務会計論160点
合計340点(68%)
こんな感じです。ボーダーはその時々で上下するので、あくまで勉強配分の目安としてみてください。
※2022年12月追記、管理会計が易化傾向にあるようです。この場合70点(理論1ミス、計算最低5問)程度は必要になってくると思います。
…「財務でそんな点数とれるなら苦労しねーよ!!」と思う方が多くだと思うのですが
社会人受験生で短答式に合格しようと考えたら上記の配分でしか基本的に合格できません。
これは下記の理由からです。
①財務会計論のみ配点が200点ある。
→私たちにはとにかく時間がありません。
効率性という観点から、最も点数配分の大きい科目を得意科目にすることが合理的です。この戦略レベルで暗記科目に逃げるような不合理な選択をしてしまうと、日々の問題演習レベルですら合理的な選択をするメンタルを維持できなくなり、結局自分が損するのであきらめて財務会計論と心中してください。
②点数の再現性が高い
→ほかの3科目の点数の再現性が低い為です。
企業法…言わずもがなの暗記科目、昨日まで覚えていても本番の選択肢で確信できるレベルの知識が定着していないと間違える可能性が高い。下記の2科目と比べると比較的再現性は高い。
監査論…理解科目の皮を被った暗記科目、企業法と違い「文章を暗記する」イメージが強いため、そもそも暗記ですら苦労する。テスト本番の選択肢の表現次第で暗記した部分でさえ運ゲーに突入する。
管理会計論…時間がない。計算問題の「取捨選択」が鍵となる科目。ばらつきはあるが高難易度の計算問題が多く出題されることから「判断力」が問われており「問題を解く力」が問われている試験ではない為、「問題を解く力」を鍛える日々の勉強とは相性が悪い科目です。
※2022年5月短答から易化したようです。この傾向が続くなら計算問題の再現性が上昇するため、重要性は一層増します。
財務会計論…200点あり、時間内に解ききることが十分可能なボリューム。計算は理解していれば問題なく正解にたどり着ける。理論問題も理解重視(会計基準を理解しているか)な問題が多い為、
ピンポイントで単語を覚えていないと解けないような問題が少ない。
合格までの効率性・時間を投入した勉強が点数に反映されるか(再現性)という2つの観点から、財務会計論の勉強を最も優先することが合格への近道です。
✔勉強方法(日々の勉強レベルの戦略):
インプットの時間を極力削ってください。つまり「授業を受けない」ことという戦略を採用します。→具体的には問題集をといて、解説を見てもどうしても分からない部分だけ10分間映像授業を見てください。
この戦略のメリット
・授業を受ける時間をすべてスキップできるため、勉強時間を500h~1000h弱カットできる
・上記の結果、問題演習という面において専念組と同様の時間を確保できる。
デメリット
・問題集には載っていない講師独自の工夫やコツを知ることが出来ない
・自分の理解が根本的に間違っていることに気づけないまま勉強をすすめてしまう可能性がある。
この勉強方法の根拠:
僕は大原の経験談しか出来ませんが、授業を受ける(見るだけ)で300時間程度は吹き飛びます。その300時間視聴した後に短答式試験の過去問を解いてみると、得点率30%くらいの結果になると思います。点数に全く結びついていません。なんなら会計士の勉強を全くしていない人でも一般的な社会性があれば25%~30%は取れると思います。
仮に300時間で監査論と企業法の問題集を150時間ずつ解いたら、この2科目に関しては60%の得点率に到達できます。なんとなくイメージできると思います。1科目150時間やるということは1か月間毎日5時間その科目だけを勉強する感じです。
私たち社会人受験生の勉強可能時間は
・1週間で40時間
・1か月で160時間
・1年で1920時間
このうちの300時間を投入して、リターンがほぼゼロなのは厳しすぎます。
今まで皆さんがやってきた勉強といえば授業を受ける→試験が大体だと思うので、「授業そのものをスキップする」という戦略には抵抗感があるかもしれませんが、やってみると高効率な勉強法であることを実感できると思います。

とりあえず授業は聞きたい!という派の人は頭の片隅にでも置いておいて下さい
社会人受験成功に欠かせない要素
受検友達を必ず作ってください:
特に受験に専念できている成績優秀者と仲良くなってください。授業をほとんど受けないという戦略上、普通に授業を受けている人がみんな知っていることを自分だけが知らないという、機会損失のデメリットを最小限に抑えるために友達作りは必要不可欠です。
特に語呂合わせや、暗記に最適なマトリックス図を自分だけが知らないのは危険です。少しでも工夫の余地がありそうな論点は、都度友達と議論し特別な工夫をしていないか探ってください。
人生がかかった友達作りです。極端な言い方ですが、付き合って成績が伸びるのかという観点がとても重要になります。

そもそもどんな予備校にしようか迷っている人へ
まとめ
✔時間が無い以外にデメリットは無い
✔1日4時間~5時間、休日10時間で。週40時間が目標
✔財務で勝つ
✔授業を聞く→問題。ではなく、問題を解く→教科書or質問が効率的
✔情報の機会損失を防ぐために、友達作りを
以上です!
働きながらの受験は、勉強時間だけ確保する根性があれば大体何とかなります。
1ヶ月続けられれば、年末以外でルーティーンが崩れることがありません。
気が付けば合格が現実的に見えてくる位置まで到達しています。
環境・戦略面をぜひ整えてアクセルを踏んでみてください!